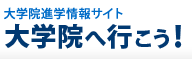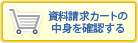研究科・専攻
人文学研究科
大阪大学大学院人文学研究科は、5つの専攻(人文学/言語文化学/外国学/日本学/芸術学)から成り立っており、人文学の役割が変化する現代社会において、思想・歴史・文学・言語文化・社会・芸術など多領域にわたり超横断的な学びの場を提供し、国際的な相互理解を推進する研究者・高度専門職業人を育成します。
ミッション
今日、高度なIT基盤社会の到来、環境の危機的状況、少子化・高齢化、世界で進む分断と閉塞など社会や国際情勢が激変する中、人文学の役割も変化の時を迎えつつあると判断できます。人文学研究科では、教育体制を時代に即してバージョンアップし、文系・理系の分断を越えて、大阪大学の諸学の基礎となり、今日のグローバル社会を支えていく「新しい人文学」を構築します。具体的には、下記のようなミッションに取り組んでいきます。
- 文学、言語、歴史、芸術、地域研究等に関わる深い人文知を継承しながら、今日的課題に果敢に挑戦し、グローバル社会で活躍できる人材を育成します。
- 人文学を最先端の科学技術と合体させたデジタルヒューマニティーズなど、新人文学分野を開拓します。
- 教養教育を所掌する全学教育推進機構等の学内組織と連携し、大阪大学のすべての学生に、文理の別にかかわらず社会人として必須のリベラル・アーツとしての人文学教育を開いていきます。
- 多様なリカレント教育プログラムを開発し、高度な人文知を社会全体へと開いていきます。
特色:「人文学林」の設置

安定した教育プログラムを提供する5専攻群(人文学/言語文化学/外国学/日本学/芸術学)に対して、社会のニーズにすばやく対応し、社学連携活動を実施したり研究グループを立ち上げるなど、研究科全体の教育体制を俯瞰して共通科目を統括する機能を持つ組織である「人文学林」を設置しました。「人文学林」では、4つの学問分野(言語科学・コミュニケーション系/思想・時空環境系(歴史・地理分野)/思想・時空環境系(哲学・思想分野)/文化表象系)と4つの地理的エリア(日本/アジア・アフリカ/アメリカ・ヨーロッパ/エリア横断)を組み合わせて16に区分された「学術マトリックス(右図)」を設けており、教員はその16の区分に配置されています。学生は所属専攻の垣根を超えてそれぞれの興味関心に従って横断的に学ぶことで、専攻を超えた交流や研究の振興が可能となります
育成する人材像
5専攻および人文学林によるシナジー効果によって、従来からの人材(大学・研究機関所属の専門的研究者、国内外の各種民間企業など)に加え、情報観、価値観、職業観、生命観、ジェンダー観などの変化や揺らぎといった、現在の社会や国際情勢の変化に対応する多様な人材を育成します。
- 全専攻×デジタルヒューマニティーズ(DH)
研究科共通科目として「DH基礎」「DH演習」等の科目を開講することにより、研究科全体でDHの手法を身につけた修士・博士人材を創出します。 - 日本学の視点から教育・研究を学際的・国際的・社学連携的に展開
全学組織の「グローバル日本学教育研究拠点」と連携して、学際的・国際的・社学連携的な教育プログラム・研究プロジェクトを多彩に展開し、高度な発信力・実践力を備えたグローバル人材を育成します。 - インターンシップ導入による企業との交流と新しい人文学の人材創出
「人文学実務研究」と「人文学インターンシップ」の2種の研究科共通教育科目を設置し、さまざまな業種の企業との交流を活性化していきます。
5専攻紹介
以下の5専攻に分かれて専門知を高めると共に、「人文学林」を通じて他専攻と共働する研究・教育を行います。
人文学専攻(博士前期課程、博士後期課程)

人間性の「知」に関わる総合的な研究・教育
下記のコース・プログラムからなる人文学専攻は、「人文(humanities =人間性)の知」に関する総合的な研究・教育を展開します。それぞれの学術的文脈に即した先端的かつ独自な研究・教育を継続するとともに、現代社会の諸課題に応えるための研究アプローチを積極的に取り込み、伝統的な人文知の更新を目指します。
■哲学コース
哲学・思想・文化に関わる研究・教育を基礎/応用の両面から展開します。基礎に関係する専門分野には「哲学哲学史」(近現代西洋哲学を中心とした研究)「中国哲学」「インド学・仏教学」があり、厳密な文献読解に基づく古典研究を柱としています。応用に関係する専門分野には「科学技術社会論」(科学技術が社会に提起する諸問題について研究する学際的分野)「臨床哲学」(社会現場との関わりを重視する哲学)があり、哲学的な視点から現代社会の諸問題に取り組む試みです。
■グローバルヒストリー・地理学コース
東洋史学・西洋史学・人文地理学の3専門分野では、古代から現代まで、またミクロな地域社会からグローバルな構造的連鎖まで、学際的で先端的な研究方法を学びます。大学全体に開かれたグローバルヒストリー副プログラムに加えて、地域密着型のフィールドワークや、情報化時代の素養を身につけた人材を養成します。また、「歴史・地理教育プログラム」を設け、中高教員と連携して、市民に開かれた歴史・地理研究を目指します。
■文学コース
「英米文学」「ドイツ文学」「フランス文学」「中国文学」(「テクスト表現論」グループ)と、世界と日本の文学を対象とする「テクスト環境論」の5つの専門分野からなります。どの専門分野においても、従来の文学研究の手法を継承するとともに、民族、地域、言語、階級、ジェンダーの境界を超えた「越境の文学」の研究を目指します。また、文学作品のみならず、音楽、演劇、絵画、建築、漫画、映画など広い意味での「テクスト」を研究対象とします。
■比較・対照言語学コース
本コースでは、言語の共時的・通時的分析の方法を学びます。共時的研究では、現在の英語、日本語などのいくつかの言語を対照させることによって、言語に関する規則性・法則性を発見することを目標とします。通時的研究では、英語をはじめとする印欧諸語等の歴史的発達に関する知見を得ることを目標とします。いずれのアプローチにおいても、十分な言語データ・資料に基づいた理論構築を行うことを重要視しています。
■実践人文学プログラム
人文学専攻では、2026年4月に「実践人文学プログラム」を博士前期課程に創設します(定員は若干名)。複数分野の知識と独自な観点からの研究を通じて得られた知見を積極的に社会に還元する人材の育成をめざします。入学者選抜は研究計画の具体性と独自性を問う「研究プロポーザル」と口頭試験によって行います。また、修士論文に代えて、創作、翻訳、研究レビュー、教育活動報告などを含む幅広い内容と形式を許容する「修了研究」を課します。
言語文化学専攻(博士前期課程、博士後期課程)
今日的な課題に幅広い観点から取り組むカリキュラム
伝統的なディシプリンにとらわれない「言語文化学コース」は、3分野にわたる6講座を有し、全講座が連携しながら、新たな研究領域や研究方法論を探究し、言語と文化に関する高度な教養や情報活用能力を修得することで、今日の多文化・多言語社会における国家・民族・文化間の諸問題などに取り組みます。
■言語文化学コース
分野Ⅰ:
【超領域文化論講座】
古代から現代にいたる文化・社会・思想・歴史に関する様々な事象や概念を、学問領域の枠にとらわれない広い視点で探究し、文化の形成と変容の諸相を多角的に究明するための総合的な知の体系の構築を目指します。具体的には、ジェンダー、人種、エスニシティ、ネーション、エコロジー、多文化共生、歴史と記憶、植民地主義とグローバリゼーション、その他のテーマをめぐる言語文化実践を考察の対象とし、文学・文化理論とフィールドワーク、思想史・社会史、精神分析学、人類学、環境人文学など様々な学術分野との関連において、超領域的な視座から考究する力と感性を養成します。
【表象文化論講座】
活字や映像をはじめとする各種のテクストや表象について、その多元的な生成・受容・伝達の仕組みを分析し、多種多様な文化現象の解明を目指します。具体的には、異言語・異文化接触において生じる文化変容や翻訳・翻案の研究、異なる地域や民族が有する言語文化の通時的・共時的諸相の比較、文化産業・大衆文化・メディア文化の動態の体系的考察を行います。
分野Ⅱ:
【コミュニケーション論講座】
現実の社会において発生する様々な問題を「コミュニケーション」の観点から調査するとともに、その問題を克服してより公正な社会を目指すための実際的技能と、言語に関連する諸科学の立場から導かれる理論との融合を試みます。多言語・多文化がひしめき合う現代社会において共生を可能にする言語文化リテラシー、およびコミュニケーションのデザイン力を追究します。
【第二言語教育学講座】
 第二言語教育学講座は、人がどのように母語以外の言語を使い、学び、そして教えるのかを研究する講座です。実際に使用するための第二言語教育に重点を置きながら、社会的・心理的・文化的な側面も研究領域に含めます。
第二言語教育学講座は、人がどのように母語以外の言語を使い、学び、そして教えるのかを研究する講座です。実際に使用するための第二言語教育に重点を置きながら、社会的・心理的・文化的な側面も研究領域に含めます。
2つ以上の言語を用いる機会が増加している現代において、第二言語の実践と理論に関する問題を読み解き、専門家として対処できる能力を涵養します。
分野Ⅲ:
【理論言語学・デジタルヒューマニティーズ講座】
自然言語の仕組みや構造を解明するとともに、人間の言語能力の真相に迫るための普遍的規則や原理を科学的に分析記述し、共時的ならびに通時的な視点から言語体系を明らかにするための研究を行います。また、言語データや文化資(史)料をデジタル処理・解析するための理論的枠組みや方法論の精緻化を進めます。数理的モデリングや機械学習を高度に応用して大規模テクストコーパスやデジタルアーカイヴの潜在的特徴を発掘する分野横断的、巨視的分析と、理論言語学、文化学的知の蓄積に基づく洞察、微視的分析を相補的に組み合わせることにより、知見の科学的 reproducibility/replicability を担保する客観的事実、証拠に立脚した言語文化学の研究を行います。
【言語認知科学講座】
人間がどのように外界を認知し、知識を獲得しているのか、またさまざまな情報を処理しているのか、言語の情報処理の観点から人間の認知的システムを科学的に捉えることにより、人間の認知メカニズムのひとつとしての言語能力の仕組みと働きについて研究します。また、言語学においてこうした観点に立つ認知言語学について、理論的枠組みと具体的な言語研究への適用との両面にわたって研究します。
外国学専攻(博士前期課程、博士後期課程)
24の言語とその地域について多角的・徹底的に学べるカリキュラム
外国学専攻は、24の言語とそれを基底とする文化一般について、さまざまなディシプリンと実践にわたって総合的に教授・研究する「外国学研究」を主眼とし、人文社会科学諸分野のディシプリンの成果を応用しつつ、世界の諸地域の言語と文化の特徴を考察し、世界で活躍する人材を育成します。
■地域文化研究コース
本コースは、研究対象とする言語・地域によって「アジア・アフリカ言語文化コース」と「ヨーロッパ・アメリカ言語文化コース」に分かれています。多様な言語、文化、社会を対象とした科目とともに、特定地域の言語社会について知見を広め、実践力の強化と研究の高度化を図る科目、さらに、多角的な研究視座を養うため、個別の言語文化圏を超えて社会の関心と時代の要請に応える科目を開設しています。高度な言語運用能力を身につけるとともに、研究対象とする言語圏についての広く深い知識を土台に、物事を多角的に見る目を養いながら、言語学、文学、歴史学、社会学などの諸分野、またそれらの学際的なアプローチに焦点を当てた教育を実践します。それぞれのコースで対象とする言語は以下の通りです。
【アジア・アフリカ言語文化コース】

中国語、朝鮮語、モンゴル語、インドネシア語、フィリピン語、タイ語、ベトナム語、ビルマ語、ヒンディー語、ウルドゥー語、アラビア語、ペルシア語、トルコ語、スワヒリ語
【ヨーロッパ・アメリカ言語文化コース】
ロシア語、ハンガリー語、ドイツ語、デンマーク語、スウェーデン語、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語
■高度専門職業人コース
本コースは、博士前期課程のみのコースであり、「英語教員リカレント・コース」と「中国語教員リカレント・コース」に分かれています。中学校または高等学校の現職の英語・中国語の教員もしくは教員免許取得者を対象とし、高度な専門的知識を持つ職業人を育成することを目指しています。
[ただし博士後期課程にはコース区分はなく、各言語・地域を対象に特別研究を行います。]
日本学専攻(博士前期課程、博士後期課程)
基盤的研究と応用的展開の双方をカバーする日本最大規模の日本学専攻
5分野から成る「基盤日本学コース」と、3分野から成る「応用日本学コース」の2コースを擁する日本学専攻は、日本の言語・文化・社会・歴史・文学などを厳密に学問的な方法に基づいて深く探究するとともに、その専門的知見に基づいて日本の抱える今日的課題に果敢に取り組むことのできる人材を育成します。さらに、比較や交流の観点から日本を世界的視野のうちに捉え、日本語・日本文化についての幅広い知見を基礎としてグローバルに活躍できる実践力・応用力を養います。
■基盤日本学コース
本コースは、現代日本学、日本史学、考古学、日本文学・日本語史学、基盤日本語学の5分野から成ります。ディシプリン・ベースの厳密で学問的な研究方法をしっかりと身につけながら、日本の言語・文学・歴史等について深く学ぶことができます。また、日本の文化や社会への現代的・学際的関心を幅広くカバーする多彩な授業も用意されています。基盤的研究能力を養いながら日本について深く広く学びたい方の期待に応えるコースです。なお、本コースの授業は豊中キャンパスで開講されます。
■応用日本学コース
 本コースは、比較日本学、応用日本語学、日本語教育学の3分野から成ります。視野を世界に広げながら日本について深く学び、日本語・日本文化についての幅広い知見を基礎として日本と世界を結ぶ力を養います。日本の言語や文化や社会について深く学びつつ、グローバルに活躍できる実践力・応用力を身につけたい方の期待に応えるコースです。なお、本コースの授業は箕面キャンパス(OUグローバルキャンパス)で開講されます。多くの留学生とともに学ぶことができる点も、本コースの特長の1つです。
本コースは、比較日本学、応用日本語学、日本語教育学の3分野から成ります。視野を世界に広げながら日本について深く学び、日本語・日本文化についての幅広い知見を基礎として日本と世界を結ぶ力を養います。日本の言語や文化や社会について深く学びつつ、グローバルに活躍できる実践力・応用力を身につけたい方の期待に応えるコースです。なお、本コースの授業は箕面キャンパス(OUグローバルキャンパス)で開講されます。多くの留学生とともに学ぶことができる点も、本コースの特長の1つです。
芸術学専攻(博士前期課程、博士後期課程)
基礎と社会的実践の両方に立脚、国立総合大学最大の芸術学の専攻

4コースから成る芸術学専攻では、他の何ものによっても代替不可能な営みである芸術を、全国的にも類を見ない規模で捉え、専門的・先端的且つ学際的な厚みと多様性を備えた研究・教育活動を行います。これにより、現代社会の諸システムの制約や限界を超え出る可能性・構想力を持った人材を育成します。
■アート・メディア論コース
作品を広範な社会環境のもとに連れ戻し文化政策・芸術計画の視点から考察すること、あるいは日々変貌するコミュニケーション技術のなかから新しい芸術理念やジャンルが立ち上がってくるさまをつぶさに目撃すること。本コースは文字通りアートとメディアの交差点に身を置きます。
■美学・文芸学コース
美学分野では、感性・美・芸術にまつわる問題について哲学的に考察したり、現代アートについて議論したり、工芸やデザインに関係する事柄について研究したりできます。文芸学分野では、幅広く古今東西の文学や思想・文学論を対象とした研究ができ、また西洋古典学にも専門的に取り組むことができます。
■音楽学・演劇学コース
音楽学も演劇学もともに我が国の総合大学において稀有な存在です。音楽文化、演劇文化全般をジャンルの隔てなく扱い、それらを広く表演芸術(パフォーミング・アーツ)としてとらえて、歴史学、人類学、社会学、美学、文学などの隣接諸科学との関係の中で研究を進めています。
■日本東洋美術史・西洋美術史コース
絵画、彫刻、工芸はもとより、写真や映像、建築、庭園など、あらゆる「イメージ」を研究対象としています。作品の様式や意味についての研究、制作の背景や受容の歴史など、さまざまな観点から、作品の的確な観察に基づいた実証的研究を行っています。
◆本研究科の入試情報はこちらから
https://www.hmt.osaka-u.ac.jp/exam/guide/