先輩の声

博士前期課程
張 曦文さん
2022年、雲南大学日本語学科に在籍中(4年生)、三重大学へ交換留学生として来日。そこで、中国と日本の社会福祉制度の違いに関心をもつ。2023年、雲南大学日本学科を卒業。同年、神戸市外国語大学 外国人研究生として来日。2024年4月、大阪商業大学大学院 博士前期課程に入学。
社会福祉を研究される先生と出会ったことで、未来が拓けた
この研究科を選んだ理由をお聞かせください。
中国の雲南大学で学んでいた時、私は三重大学に交換留学生として来日しました。社会学を学ぶなかで、少子高齢化が進む現代における社会福祉に興味をもつようになりました。そこで、この分野を研究されている先生を紹介してもらいました。その先生が今、大学院で私の研究を指導くださっている宍戸先生です。
大阪商業大学大学院は、日本と中国の比較研究をしている実績も多いと知り、留学後の研究がスムーズに進められるのではないかと考えました。大学院に入るための事前面談において、宍戸先生は私の研究したいことをとてもよく理解してくださいました。
研究テーマは、東アジアにおける高齢者福祉や高齢者互助システムの比較です。日本の社会福祉制度は世界でも進んでいますし、社会保障制度も充実しています。地域包括ケアシステムなど、とくに地域の互助・福祉制度が進んでいると感じます。中国にも社区という互助の仕組みがあるのですが、まだ互助システムを整えて活用していくために、必要なことを模索している段階です。
日本、中国、台湾などで調査研究を進め、日中国際シンポジウムで研究報告をしました。北東アジア学会に論文を投稿する機会もいただき、学会賞を受賞することができたことも自身の励みになっています。
 |
フィールドリサーチに力を注ぐことができる環境と手厚い支援
この研究科で学ぶメリットを教えてください。
フィールドリサーチなど実践的な研究に力を注げることが大きいです。研究を進める上で、社会現場の実態調査は欠かせません。私は、社会福祉施設や地域包括支援センターなどを訪問し、現状と課題を分析しています。専任教員の先生方が、自らのネットワークを駆使し、フィールドリサーチできる場を紹介してくださいました。こうした支援をしてくれる大学院の環境は、とてもありがたいです。
フィールドリサーチで得られる社会の実態には、興味深い内容が多くあります。社会福祉施設や介護施設の現場では、資金やボランティアの不足という問題に直面していることなどもわかりました。
先生方が連携して指導くださっていることも、この大学院で学ぶメリットです。研究指導を担当いただいている宍戸先生はもちろん、地域経済政策専攻の先生方が、様々な専門分野の知識や情報を惜しみなく私たち院生に与えてくださいます。書いた論文についても、多方面からのフィードバックをいただけるので、視野が広がります。少人数制の大学院ならではの手厚さと、オープンな環境を実感しています。
人前で発表する機会を重ね、語学力が飛躍的に向上した
身に付いた知識・スキルはどんなことですか。
語学力がレベルアップしました。これまでも日本語を学んできたので、読むことにはある程度自信はありましたが、人前で話すことは苦手でした。自分が言いたいことを言葉にして伝えることは難しいものです。大学院に進学してからは、学会などで研究を発表する機会をいただき、それに向けて猛勉強をしました。自分の言いたいことやその単語を調べて、それをメモして声に出す。より相手に伝わるようにするにはどうしたらいいかを考えながら、何度も繰り返し練習し、身につけるようにしました。
研究の合間に介護施設でアルバイトをしていますが、そこには、生の日本語が飛び交っているので、そこでコミュニケーションをとっていることも、日常会話のレベルアップにつながっています。
研究に専念できる環境も、レベルアップの要因の一つだと思います。少人数制の大学院なので、授業によっては先生とマンツーマンの授業もあります。言葉の壁がある留学生の私にとって、手厚いサポート体制だと感じています。研究室は、パーテーションで仕切られた個室感覚のブースなので、集中して取り組むことができます。
レポートや発表論文では、文章を書く能力も求められます。先生方に教えていただき、日本語の論文形式について、構成の組み立て方などを学びました。今では、ずいぶんスムーズに書けるようになったと思います。
まずは現場で経験を積み、将来は研究職をめざす
修了後の目標をお聞かせください。
卒業後は、福祉関係の仕事に就きたいと考えています。先生方からもアドバイスをいただき、まずは社会福祉施設や介護施設に勤めて、現場での経験を積みます。そこで、社会福祉士や介護福祉士など日本の国家資格の取得もめざします。施設の運営にも関わりながら、働きたいです。そうすることで理論だけでなく、現場で働くという実践でこそ得られる知識やスキル、見えてくる課題もあるからです。現場経験を積む中で、新たな研究テーマも見つかるはずです。発見したテーマをもとに、今後さらに博士後期課程で研究を続けることができればと思います。
将来は、日本と中国の社会福祉や社会保障制度など比較研究する研究職に就くことをめざしています。日本は社会福祉制度の充実はもちろん、地域におけるコミュニティとの連携がとれているところが素晴らしいです。日本の先進的な仕組みを研究し、その結果を中国に持ち帰って、社会福祉制度や相互扶助の仕組みを整えていくことに貢献していきたいと考えています。
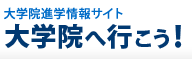
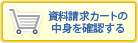
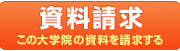
 地域政策学研究科
地域政策学研究科 地域経済政策専攻
地域経済政策専攻

